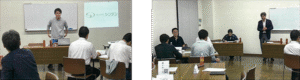Posted on 2025年11月12日(水) 12:02
発行日:2025年 10月31日
発行者:栃木県中小企業家同友会
〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13
TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827
E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp
URL:https://www.tochigi.doyu.jp/
企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所
※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。
Posted on 2025年11月12日(水) 11:54
News Topic 01 栃木のNEWS
県央支部9月例会
「社員と一緒にまなぶ」をまなぶ
●合同入社式の参加企業が登壇
9月16日(火)、宇都宮市東市民活動センターを会場に県央支部9月例会が開催された。いつもの例会は報告者1名のケースが多いが今回は3名。しかしながら当日は諸般の事情で、株式会社シンデン:専務取締役八木匠氏と、株式會社総研:代表取締役小岩圭一氏の2名の報告となった。
企画の発端となったのは「合同入社式」。それぞれの会社に新人社員(新卒・中途)として入社した方々が一堂に介し、新しい門出を会員企業同士で祝い、また、多くの仲間とスタートするよろこびを分かち合う、そんな思いを込めた栃木同友会の恒例行事の一つである。
報告者は合同入社式に参加した会員企業で、内容を大きく①「新入社員が会社に与えた影響や変化」②「合同入社式がもたらした効果やメリット」③「経営者として『人を育てる』ことへの考え方や覚悟」の3 つに分けて報告があった。
●若手人材の個性と真摯に向き合う
報告の口火を切ったのは(掬シンデン:八木氏(以下敬称略)。十代~二十代までの若手の新卒・中途採用者、計3名のケースを紹介した。合同入社式は、既存社員が新入社員に話を振るときの話題になるなど、社内コミュニケーションの向上にひと役買っているという。
一方、本人の事情により退職または休職中の新卒者が出るなど、若手人材を長期的に雇用することの難しさを惑じる面もあるとか。人は趣味や個性、経歴や歩みも十人十色で、採用はそれらについて一人ひとり、緻密かつていねいに向き合うことが大切と話す。
また、採用後の手続きには各種書類が必要になるが、ある新人社員とのやりとりをきっかけに公的機関の発行手数料を自社で負担することにし、あわせて就業規則を一部変更した。実態に沿ってスピーディーに対応策を講じるなど、柔軟かつ機動的な同社の一端を知った。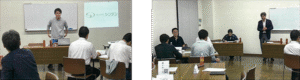
●これから働く新入社員にエール
続いて(株)総研:小岩氏(以下敬称略)から報告があった。令和元年に創業50周年を迎えた同社は「共に次の50年、地域で輝く100 年輝業へ」を10年ビジョンに掲げ、全社員一丸となって新たなスタートを切った。
同社は、環境・建築・土木・測量・補償.鑑定などの総合コンサルタントとして、幅広い分野のスペシャリストが在籍する、いわば“専門職業家集団”である。
有資格者の社員の中には、自身のスキルを活かし、独立開業したり、同業他社へ転職する人も少なからずいるという。そのため継続的な専門人材の採用・育成は企業活動の生命線ともいえ、かねてより特定分野に絞り込む形で採用活動を行ってきた。
合同入社式への参加は、これから働く新入社員にエールを送る意味でも、また、長期雇用を念頭に中長期的な視点での組織づくりにも欠かせないという。実際に合同入社式は、自社の組織運営にプラスの効果をもたらしているそうだ。
また、同友会での学びを組織づくりに活かしている点にも注目したい。周年記念行事でグループ討論会を行い、社内委員会では多様な学びの機会を提供するなど、小岩氏は自らの学びを会社そして社員に還元している。
お二人の報告の後、それぞれの事例をテーマに話し合うグループ討論へ。人材や採用をキーワードに、中小企業ならではの悩みを本音で語り合い、学び合う、熱のこもった例会となった。
[文責]鈴木 正則]
アデラ・コンテンポラリー
Posted on 2025年11月12日(水) 11:27
News Topic 02 栃木のNEWS
県南支部9月例会
「拡大から承継へ」
一福田会員の問いかけから生まれた次の10年ビジョン
去る9月17日(水)、会場「あいとびあ」にて、参加者11名で県南支部例会が開催されました。
好評につき回を重ねている「営業ってどうしてます?」シリーズの第3弾となる例会です。
その例会において「5年後、どのように顧客を拡大したいですか?」と問われました。参加者の多くは拡大や現状維持など外部環境に基づく答えを語る中で、私が気づいたのは「内部環境」への視点でした。
弊社はベトナム・インドネシア・タイを中心とした人材紹介および派遣業、日本語学校の運営を手掛ける外国人材専門サービス業を行っています。
私自身も独立創業して来年で丸20年になろうとしています。これまでにはリーマンショック、東日本大震災、そしてコロナショックといった大きな危機もありましたが、何とか乗り越えて経営を維持してきました。
コロナ禍を経て5年が過ぎた今では、おかげさまで顧客は拡大しました。今後は自然消滅分を補う20%の拡大を見込みつつ、重点は人材育成と組織づくりに置いています。トップセールスが獲得した顧客を新しい人材に引き継ぎ、社長がいなくても自走できる体制を整える。これが私の描く5年後の姿です。
過去に中途採用を試みても失敗したのは、人材ではなく私自身の「現場への執着」が原因でした。そこで自問しました―どうすれば執着を手放せるのか。答えは「自分が不在になる状況を想定する」こと。もし2か月入院するなら、その間に会社が動く仕組みをつくる必要があります。この発想が覚悟を促しました。
さらに思索は10年先へ。2020年時点でのビジョンは「拡大」でしたが、50歳・経営20年の節目を迎えた今、必要なのは「承継」。次の10年は、社員に安心を残し、子どもに選択肢を残す10年だと悟りました。孔子の「五十にして天命を知る」と重なり、「仕事をつくり、人材が輝く場をつくり、未来を変える」というこれまでの経営理念も次のように、より具体化することができました。
・アジアの若者に「日本への希望の道」となる仕事をつくる。
・栃木県に住む人々が輝く「国際化と教育」の拠点をつくる。
・そしてアジアと栃木県の距離をなくし、明るい未来へと変える。
例会進行役の福田会員が説いた「営業とは相手の潜在的ニーズを掘り起こすこと」。今回の問いかけを通じ、自分自身の潜在的ニーズを発見できたことが最大の成果でした。
拡大から承継ヘ―これが次の10年の覚悟です。そんなことを考えるきっかけとなった9月県南支部例会でした。
[文責]行廣 智明]]
(株)行廣国際アカデミー 代表取締役
Posted on 2025年11月12日(水) 11:17
News Topic 03 栃木のNEWS
経営指針をつくる会の終了
経営指針をつくる会が終わりました。
4か月にわたって行われた「第11回経営指針をつくる会」が、全9回の予定を終え、無事に修了いたしました。今回も受講された皆さん全員が最後までやりきることができ、本当にうれしく思います。
栃木同友会の「経営指針をつくる会」では、特に“現状を正しく知ること”に力を入れています。どんなに大きな夢や希望を持っていても、それを実現するための土台がしっかりしていなければ前に進むことはできません。けれども、自分がどんな土台の上に立っているのかをしっかりわかっている人は、意外と少ないものです。いま自分がどんな場所に立っているのかが見えれば、「何をしたいのか」「何ができるのか」「どうやってそこにたどり着くのか」がはっきりしてきます。
そのため、この講座では全体の約6 割の時間を、自社の現状を確認することに使っています。自分の会社の立ち位置や強み・弱み、課題が見えてくると、これからどんな方向に仕事を進めていくのかが自然と明確になってきます。そうすると、理念づくりや計画づくりもスムーズに進められるようになります。

これまでの「つくる会」では、社員との関わり方についで悩む経営者の方が多くいらっしゃいました。今回も同じような課題が出てまいりましたが、社長の考え方がしっかり定まっていれば、あとは「どう伝えるか」という点に集中できます。そのため今回の講座では、実際に社員に話す場面を想定して、ロールプレイ(模擬練習)を行いました。方針を決めるだけでなく、実際に人と向き合って話す練習をすることで、自分の伝え方の課題や改善点を見つけることができました。
「経営指針をつくる会」は、自分の考えを言葉にして整理し、確かめることができる貴重な時間です。毎年6 月ごろから9 月ごろまで開催しております。これからの大きな変化の時代に、自分の会社を見つめ直したい方は、ぜひ一度参加してみてください。きっと新しい気づきや、思いがけない発見があるかもしれません。
[文責]石綱 知進]
経営労働委員会 経営指針をつくる会担当
Posted on 2025年11月12日(水) 11:06
News Topic 04 栃木のNEWS
経営指針をつくる会の感想
経営指針をつくる会を受講して
8月20日(水)県南支部例会を開催しました。
正直に言うと今まで「経営指針をつくる会」への参加を様々な理由を付けて避けていた。経営指針が重要なのは分かっていたが、心の奥で参加することで自分自身が変化しなくてはいけなくなることに抵抗していたからだと思う。しかし終わってみれば「参加して良かった」の一言である。
現状認識の講では内部環境・外部環境が業種によって多種にわたるが、自分では気が付かないこと、知らないことが多くあった。そしてそれがその業種だけではなくお互いに影響していることや根本的な課題の多くは同じであることに驚いた。また、宿泊で行われた自己認識の傾向を探った時も「悪・浅野」が垣間見え冷や汗をかいたが、自分を冷静に俯廠して見る訓練になったと思う。
つくる会はとにかく「自分で考える」「自分の言葉にする」「自分で決める」の繰り返しで、かなり脳に汗をかいたが、自分の中では「事実と推測と感情を書く」宿題を週2 回提出することがとても辛かった。
今回、経営指針をつくるに当たって、サポーター方々の「薬局の本筋って何?」という一言が最も心に聾いた。自分自身が「地域」という言葉に拘りすぎていて、本質の「患者」「スタッフ」に目が向いていなかったことに気付かされました。
このように、講師やサポーターの方々が課題や解決策を自社の事のように親身に考えてくれたおかげで、大変さはあったが楽しく有意義な学びが出来ました。
今後はこの会で学んだ内容と作成した経営指針を経営に生かし「共に学び成長できる」「社員の家族が働きたいと思ってくれる」会社にしていき、患者さんからは「この薬局に来て良かった」と心から感じてもらえるように薬局づくりを進めていきます。
最後にこの会を受講してみて多くの方にも参加して欲しいと思いました。私も今後サポーターとして関わっていけたらと思っています。
[文責]浅野 敏一]
株式会社コメノイ 代表取締役