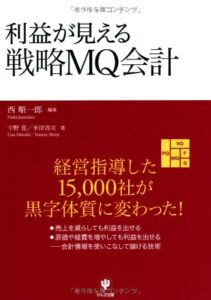Posted on 2025年9月5日(金) 13:57
発行日:2025年 8月31日
発行者:栃木県中小企業家同友会
〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13
TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827
E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp
URL:https://www.tochigi.doyu.jp/
企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所
※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。
Posted on 2025年9月5日(金) 13:53
News Topic 01 栃木のNEWS
8月県例会
 8月1日に栃木県総合文化センターで開催されました8月度県例会の様子を皆さんに報告致します。
8月1日に栃木県総合文化センターで開催されました8月度県例会の様子を皆さんに報告致します。
30名弱の方が参加しての県例会でした。
報告者としてメトロ設計株式会社代表取締役小林一雄氏をお招きして「地下鉄設計から未来環境づくりへ!~時代を乗り越える、学び合いの実践~」というテーマで1時間強の報告を頂きました。
自己紹介、自分の生い立ち、会社の紹介から始まり、次の経営理念の意味を紹介頂きました。
(経営理念)
未来環境を創る仲間
技術を未来につなげる仲間
学び合い共に成長する仲間
お父様から社長業を引継ぐ頃、市場は縮小しており、競業会社も多く登場したことから経営が悪化していたとのことです。その中での社長業の引継ぎで、事業の見直しや給与体系の見直しなど経営の立て直しに奔走されました。
競売物件で購入した自社ビルは売却ができる状況になく、如何に活用していくかを考えていた時に地域を巻き込んだ不動産事業を行うことができたと話されました。
経営の立て直しから始まって自社ビルの活用と小林氏は従業員のために活動されましたが、従業員とのコミュニケーションが少なくなっていたとのことです。その結果、不満を持つ従業員や辞めていく従業員が出ていたということです。
『従業員とのモヤモヤ!』
これは私がこれまで例会報告者の話を聞いていると感じることです。
小林氏もこの状況にあったと報告を聞いて私は感じました。
このモヤモヤが生じると何故か同友会と巡り合うのです。
小林氏も『従業員とのモヤモヤ!」時期に同友会と出会いました。
そこから同友会でいろいろ学び、上記に記載しました経営理念を作成し、この理念に賛同する従業員と伴奏しながら会社経営を走り始めた。
あっという間の報告でしたが、学ぶことが多かったです。
その後のグループ討論では「社長と社員(もしくは社外の協力者)が共に成長するために、どのような巻き込み方をしていますか?」というテーマでグループ討論を行いました。
グループは5~6グループあったと記憶しております。
それぞれのグループで自己紹介や感想、テーマについて話し合い、盛り上がりました。
その後の発表も盛り上がりました。
[文責]浅野知則
Posted on 2025年9月5日(金) 13:44
News Topic 02 栃木のNEWS
7月25日 暑気払い
7月25日倹県央支部主催の暑気払いが山泉楼にて開催されました。
暑気払いは県央支部の恒例行事ではありますが、今回は県全体の行事として開催され、県央支部以外に県央支部、鹿沼日光支部の会員も参加しました。
暑気払いのため本来は会員同士の懇親を図る目的ですが、今回は県央、県南及び鹿沼日光支部からそれぞれ各支部の紹介がおこなわれました。
紹介の内容は各支部の基本的な情報(主な活動地区や会員数など)の他、支部運営目的や支部の魅力の紹介がありました。
各支部の紹介の中で活動地区の違いなどの違いがあるものの、共通していたことは活動目的で会員が自主的に参加し、学びを得ることができるという点です。
他支部の会員からすると他支部の活動はなかなか見えにくいものですが、今回の暑気払いで他支部の活動の一端を垣間見ることができました。また、支部を越えた交流も希望しており、自分の所属していない支部への参加も進めていきたいとの話にもなりました。他支部の活動に参加することで同友会の魅力を発見することに繋がると感じました。
支部紹介の話が長くなりましたが、暑気払いの本来の目的である「会員同士の親睦」も当然行われ、仕事や同友会活動、プライベートなど普段では出てこない話もあり楽しく盛り上がりることができました。その後、有志による二次会も開催され、こちらも大変盛り上がりました。
同友会は他の異業種交流会とは違い勉強会の要素が強い会ですが、たまにはこういった懇親会も開催していきたいと思わせる暑気払いとなりました。
[文責]片平芳明
こいあい税務会計
Posted on 2025年9月5日(金) 13:35
コラム
会社経営に役立つ本:
「利益が見える戦略MQ会計」
みなさんは「会計」と聞いて、どんなイメージを持っていますか?難しそう、数字ばかりでつまらなそう、そんな印象があるかもしれません。しかし、会計は企業が生き残るために必要不可欠な‘‘言語’’です。そして、経営の戦略を支える“武器”にもなります。今回紹介する「利益が見える戦略MQ会計」は、そんな会計の本質をやさしく、そして面白く教えてくれる一冊です。
製品・サービスの価格が企業経営を決める、そんな話を聞いたことはないですか?「MQ」とは、「M =粗利」と「Q=販売数撮」を組み合わせた指標です。普通の会計では「売上」「原価」「利益」などの数字を見ますが、MQ会計では「どのくらいの粗利で」「何個売ったか」に注目します。つまり、ビジネスの現場で利益を生み出す‘‘源泉’’を分析するための会計方法です。
企業はなぜ利益を重視するのでしょうか?それは、利益がなければ長く続けることができないからです。利益が出れば、社員に給料を払ったり、新しい設備を導入したり、社会に貢献したりすることができます。逆に利益がなければ、企業はすぐに倒産してしまいます。
つまり利益が出ている黒字経営は、会社が存続するための最低限必要なことなのです。『利益が見える戦略MQ会計』では、利益がどのように生まれるかを、経営戦略と会計の視点から詳しく説明しています。
●値段を上げるべきか?
●もっとたくさん売るべきか?
●コストを減らすべきか?
こうした疑問に対して、「MQ会計」はシンプルな数字で答えをだしてくれます。
たとえば、お店でパンケーキを販売するとしましょう。
●1枚100 円でパンケーキを売る。
●1日に100 枚売った場合、売上は10,000 円。
●材料賀などを除いたら、いくら粗利が残るか?
粗利>固定費(給与+家賃+光熱賀などの物が売れなくてもかかる費用)になっていると、黒字。なっていなければ赤字となります。
このようなシミュレーションを通じて、「粗利(M) 」と「数量(Q)」、そして「利益(G) 」の関係を学ぶことができます。MQ会計は、分かりやすい数字で“利益’’を明確にしてくれるので、実際のお金の流れを理解するのに役に立ちます。
企業の経営者は、「どんな商品をいくらで、どれだけ売ればいいのか」を考えています。それも、直感だけで決めているわけではありません。『利益が見える戦略MQ会計」では、数字を使って合理的な意思決定をするための考え方を学べます。
たとえば、「値引きをすれば売れるけど、利益は減る」「広告を出せば売れるかもしれないが、費用がかかる」といったジレンマに対して、数字で効果を予測できます。
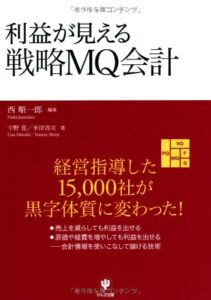
数字を味方にして、自分の行動をより戦略的に考える力を身につける手助けをしてくれます。
この本は、経営の現場で長年培った知識と経験をもとに書かれており、会計の本質を分かりやすく伝えています。
経営をする上で、価格と粗利益は最も重要な要素です。稲盛和夫氏も「値決めは経営である」とまで説いています。
皆さんも、これを機会に値決めについて考えてみてはいかがでしょうか?
[文責]石綱知進
株式会社共立 代表取締役
Posted on 2025年9月5日(金) 13:26
コラム
外国人労働者とインバウンドの現場から見える新たな風景
一行廣国際アカデミー・行廣智明社長インタビュー
かつて、近所のスーパーでは同級生の女子高校生がレジ打ちのアルバイトをしている姿が当たり前だった。しかし今では、そうした風景を見ることはほとんどなくなった。代わりに目にするのは、年配の方や若い外国人が働く姿だ。数年前から首都圏では一般的な光景となっていたが、ここ栃木県でもそれが日常になっている。
こうした変化の背景には何があるのか。外国人材の受け入れに長年携わってきた行廣国際アカデミーの代表取締役社長、行廣智明氏に話を伺った。
行廣社長は大阪外国語大学(現・大阪大学)ベトナム語科の出身で、学生時代にはベトナム留学の経験もある。卒業後は様々な事業に挑戦してきたが、一貫してベトナム人を中心とした外国人との関わり」を軸に
事業を続けてきた。現在は外国人材の人材派遣、日本語学校、専門学校の運営を手がけ、外国人材支援に関しては25年以上の経験を誇る。
外国人労働者のリアルな姿
「外国人労働者という言葉だけでは一括りにはできません」と行痰氏は語る。出身国によって価値観も目的も異なるからだ。
「日本人の多くは、彼らも日本で長く働くことを前提にしていると捉えがちですが、実際には‘‘お金を稼いで母国に帰る”という目的を持つ人が大半です。だからこそ、同じ職場で働くには、彼らの価値観を理解することが欠かせません」。
外国人材を単なる都合の良い労働力として見るのではなく、「どのように考え、何を求めて日本に来ているのか」を理解することが、共に働く上での出発点になり、外国人材との共通利益を開発できると行廣氏は強調する。
インバウンドビジネスの可能性
外国人労働者の受け入れだけでなく、行廣氏はインバウンドビジネスにも強い関心を持っている。
「最近は白馬やニセコといったスキーリゾートが外国人観光客、特に富裕層に人気です。いわゆる“観光地巡り’’をする一般客とは明らかに異なる層で、彼らは高品質な体験を求めて来日しています。そうした層をターゲットにしたビジネスの組み立てが進んでいます」。
また、現在注目されている観光地はすでに価格が高騰しており、次に狙うべきは「まだ目をつけられていない地域」だという。「価格が安いうちに魅力ある土地を押さえられれば、大きなビジネスチャンスにつながるはずです」と語る。
とはいえ、ビジネスを始めるうえで避けて通れないのが法規制との兼ね合いだ。「どんなに良いアイデアでも、法や制度に則った設計ができなければ前に進まない。法律を理解し、それに適合する形で組み立てることが鍵になります」。
「趣味だけではつまらない」人生の本質
仕事に打ち込む日々の一方で、行廣氏はかつて「趣味に全力を注ぐ」期間も過ごした。釣りが趣味の彼は、家族の理解を得て2年間、休日を釣りに費やす生活を送ったという。
「確かに楽しかった。でも、しばらくすると‘‘趣味だけの生活ってつまらない’’と感じるようになったんです。仕事があるからこそ、趣味も生きてくるんだなと実感しました。
また、私が力強く活動を続けられるのは、家族を支え、自らの夢や希望のために挑戦し続ける外国人材と誠実に向き合うことが、私自身の原動力となっているからです。」
すべては「人材が輝く場づくり」のために
行廣国際アカデミーの経営理念は明快だ。「仕事をつくり人材が輝く場をつくり未来を変える」
社長自身が、今も精力的に現場を飛び回り、実態を見て、肌で感じながら事業に取り組んでいる。
外国人労働者の受け入れにせよ、インバウンドビジネスの開拓にせよ、すべての根底にあるのは「人と向き合う」という姿勢だ。行廣氏の取り組みは、これからの地域経済と外国人材活用の在り方に、一つのヒントを与えてくれる。
[文責]石綱知進
株式会社共立 代表取締役

 8月1日に栃木県総合文化センターで開催されました8月度県例会の様子を皆さんに報告致します。
8月1日に栃木県総合文化センターで開催されました8月度県例会の様子を皆さんに報告致します。