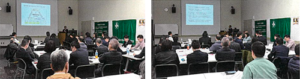Posted on 2026年1月29日(木) 15:15
News Topic 01 2026年挨拶
自分の心に水をやり、経営の畑を耕し続ける

2026年は、幕開けから激しい情勢の変化に揺れている。海外では、なりふり構わぬトランプ政権によるベネズエラヘの武力攻撃やグリーンランド領有への力の行使、イランの一凰9反政府デモヘの武力介入の示唆など、一刻も目が離せない状況が続く。
ロシアや中国の動向も不気味だ。国内に目を向ければ、衆議院選挙を控え、目先の負担減に重きを置いた政策案が先行している。
財政悪化懸念からくる円安や長期金利の上昇は、企業や家計の負担増という影を落とし始めている。人工知能(AI) の進化と浸透が効率や利便性を高める一方で、真実と偽情報を混在させたSNS の拡散は、社会の対立や疎外、分断を加速させている。総じて世相は暗い。
こうした強大な力による現状変更や支配、ポピュリズムによる民主主義の毀損(きそん)、そして対立や分断による「連帯」の喪失。この暗い世相を前に、我々はこのまま手をこまねいていて良いのだろうか。どんなに抗っても報われない経営環境があるとしても、ただそれを受け入れるだけで良いのだろうか。
ばさばさに乾いてゆく心を ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて
(「自分の感受性くらい」茨木のり子より)
中小企業家同友会は、先人たちの「中小企業は平和でこそ発展する」という教訓のもと、「中小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁栄をめざす」ことを目的の一つに掲げている。そこには、「自主・民主・連帯」の精神という、現在の情勢とは真逆の理念がある。
自主性を重んじるからには、自ら決断するための知恵を磨き、仲間と共有する。決め事は対話を重視した民主的な方法を模索し、一度決まったことは皆で汗をかいて推進する。他者を尊重し、違いを認めながらも深い信頼関係を築き、関わり合う。これらは非常に時間と手間の要ることであり、すぐには結果が出ないことも多い。
しかし、「自主・民主・連帯」の精神のもとに知恵を出し、汗をかき、関わり続けることで、不思議と道は拓けるものだ。何事も面白くなり、必ず誰かが手を差し伸べてくれる。
こうした歩みを着実に積み上げ、風土として組織に定着させていく。するとその組織は、ちょっとやそっとでは倒れない強い根を張り、確かな年輪を刻む太い幹となる。今年度の我々のテーマ「経営の畑を耕し、種をまき、根をはる一年~一年では終わらない経営の畑づくり、3年で企業づくりを~」は、まさにその風土を酸成しようとする挑戦である。
私自身の会社においても、今年の仕事始めに初めての「経営指針発表会」を開催することができた。指針づくりから発表会の開催まで、実に8 年もの歳月を要した。
しかしそれは、丁寧に経営の畑を耕し、種を蒔き、芽吹いた命を大切に育て、根付かせてきた結果だと、今なら胸を張って言える。畑に例えられる「風土づくり」や「企業づくり」の主体者は、まずは自らの心にたっぷりと水を与え、潤し、地に足を着けて、行く末を明る<照らす存在であらねばならない。栃木同友会の活動を通じて、私もまた多くの水と栄養を授かり、実践の技術を身につけることができた。
これから先、どのような事態が起ころうとも、我々中小企業家が平和な社会の先頭に立ち、まっとうな仕事で社会に貢献するという気概を持ちたい。同友会の活動を屈託なく推進することで、会社や会を通して、世の中を少しでも良い方向へ変えていく。今年一年、皆様とともに知恵を出し、汗をかくことをやり遂げたい。一年後、共に成長を実惑できる日が来ることを、今から心待ちにしている。
[文責]小岩 圭ー
栃木県中小企業家同友会 代表理事/株式會社 総研
Posted on 2026年1月29日(木) 15:01
News Topic 02 栃木のNEWS
戦略会議について
栃木同友会の戦略会議と、計画づくりの考え方
12月の第一週、今年も来年度の栃木同友会の運営方針を決める戦略会議を行いました。この会議の目的は、大きく分けて二つあります。一つは、同友会としてどのような考え方を大切にし、どの方向へ進んでいくのかを確認すること。もう一つは、各支部や委員会が一年間どのような活動を行うのかを整理し、全体として無理のない計画をつくることです。これは、なかなかに大変なことです。各人各様の意見を持っていますから、その意見をどうとりまとめるかが難しい。また、各自の意見を吸い上げることも、なかなか大変です。そこでこの会議で行っているのが、模造紙と付箋を使った意見統合です。一人ひとりが考えたことを付箋に書き出し、模造紙に貼りながら全体を整理していきます。
経営指針をつくる会でも行っているこのやり方は、考えが「見える形」になるのがいいところです。誰が何を考えているのかが分かり、話し合いが止まらずに前へ進みます。付箋を使うことで、後工程での意見集約もやりやすいのです。
世の中では「見える化が大事だ」とよく言われますが、実際には考えや判断まで見える形で進められている場は多くありません。付箋を使った方法では、意見を出しやすく、その場で中核となる問題(センターピン)を探し出したり、物事の決定を複数人で決めることができたりする、非常に実践的なやり方です。
昨年度の栃木同友会初の戦略会議は、一泊二日で実施しました。県内の多種多様な異業種交流会や勉強会の中で同友会がどういった立ち位置にいるのか、今後どのような状態を目指すべきか。そして、同友会が地域の中でどのような役割を果たせばいいのかを確認しました。合わせて、これから数年間、どの方向を目指して活動していくのかも話し合いました。
今年の戦略会議では、昨年度に決めた大きな方針はそのままに、この一年間の運営を振り返りながら、「これからどうしていきたいか」を重ね合わせて計画をつくりました。計画を立てていくと分かりますが、すべての計画が同じ重さを持っているわけではありません。中心となる計画があり、それを支える計画があります。栃木同友会で言えば、中心になるのは「総会」と「経営フォーラムJです。これらを成功させるために、支部例会や委員会活動があります。最初に中心を決めることで、全体の方向がそろい、活動の意味が分かりやすくなります。
この考え方は、実際にやってみて初めて理解できる部分が多くあります。昨年一年間、この方法で運営してきたことで、「計画の立て方が、組織の動き方そのものを決めるところがある」ということが、はっきりと分かるようになりました。
最終的には、複数の支部や委員会が同じ場所で同時に計画を立て、すり合わせを行いました。そのため、全体の流れが自然と整います。もちろん、そのためには事前の準備が欠かせません。その積み重ねがあるからこそ、短い時間でも中身の濃い話し合いができます。
こうして、同友会の考え方(経営指針) と、実際の活動、理事会の行動が同じ方向を向くようになりました。考えと行動がずれないことが、組織を無理なく動かすためにはとても大切です。会社で計画を立てるのが苦手だと感じている人には、特に役立つやり方だと思います。
私自身、細かくて長い計画を立てるのは得意ではありません。時間をかけて作っても、世の中が変わり、そのまま使えなくなることが多いからです。だからこそ、計画は軽く立て、状況に合わせて少しずつ修正していくようにしています。
この考え方を「エフェクチュエーション」といいます。先の見えにくい時代だからこそ、完璧な目標を最初に決めるのではなく、「今あるものを使いながら進み、考え続ける」ことが重要だと惑じています。
栃木同友会では、この二年間で「何をやるか」ではなく、「どうやって考え、どうやって決めるか」を変えてきました。その結果、無理のない、疲れにくい運営に形を変えてきています。
学ぶことは遠回りに見えますが、実は近道です。基本的なことを知っていれば、今やっていることの意味もわかりますし、どこをどう変えればどう変わるかもわかります。そして、行く末を見通すこともできるようになります。
栃木同友会の戦略会議では、こうした手法を使って大きな運営を進めています。
2026年度は、「経営の畑を耕し、種まき、根をはる1年~3年目の企業づくり、同友会づくり」(仮)を進めてまいります。
[文責]石綱 知進
専務理事
Posted on 2026年1月29日(木) 14:52
News Topic 03 全国のNEWS
令和8年度税制改正大綱について
昨年12月26日、令和8年度税制改正大綱が公表されました。今回の改正は、物価高対策と「税負担の公平性」という考え方が色濃く反映された内容となっています。
令和8年度の目玉は、以前より話題となっていた「年収178万円の壁」への対応です。課税の最低限度額を引き上げることで所得税の減税を行う方針が盛り込まれました。その他、法人税を含む税金全般にわたる改正案が示されており、今後開催される通常国会にて正式に可決・成立する見通しです。
そもそも「税制改正大綱」とは、毎年12月に政府が税制改革を行う際の基本方針や内容を示す文書です。新たな税制の創設や、既存の税制の延長・廃止がここで決まります。「令和8年度」と銘打たれてはいますが、数年後から適用される項目もあり、一般的には分かりづらい側面もあります。
公表直後は新聞やニュース、インターネットなどで大々的に取り上げられますが、その後はメディアへの露出が減るため、つい関心が薄れてしまいがちな存在でもあります。正直なところ、税制改正は自分に関係しない項目も多く、あまり気にされていない方も多いでしょう。いわゆる会社員などの一般納税者の方は、ご自身でコントロールできる項目が少ないため、それほど神経質にならなくても大きな問題はありません。
しかし、会社の経営者にとってはそうはいきません。例えば、法人税法における「少額減価償却資産の損金算入」の特例ですが、2026年4月から対象が「40万円未満(現行30万円未満)」に引き上げられる予定です。これは会社にとって明確なプラス要素であり、金額規模は小さくとも、着実な節税効果が期待できます。また、インボイス制度に関しても変更が予定されており、これらは消費税のみならず、実務上の手間や取引判断といった会社経営の根幹に影評を及ぼします。
このように、税制改正の多くは単なる数字の話ではなく、会社経営そのものに直結するものです。では、どこまで理解すべきかという点ですが、全体像を網羅するのは我々プロである税理士の仕事です。経営者の皆様は、税制も「経営の一部」であると捉え、自社に関わるポイントを絞って理解しておくことが大切です。
内容が複雑で分かりづらいと感じる場合は、まず顧問税理士に**「今回の改正で、自社に関係することはありますか?」**と一言聞いてみるだけでも十分です。経営者がアンテナを張り、知っておくことが、自社の経営をより良く活かすことへと繋がります。
[文責]片平 芳明]
こいあい税務会計 税理士
Posted on 2025年12月26日(金) 13:35
「何が何でも生き残る」を胸に、
激動の時代を乗り越える学びの基盤を築いた一年

2025年は、我々中小企業家にとって、経営の前提そのものが揺らぐ激変の年となった。米国の相互関税政策の本格化、胚史
的な円安と物価高騰が進行し、加えて世界情勢が不安定化する中、中小企業にとって平和があって初めて経済活動が行えるという現実を痛惑した。また、地方の停滞が加速し、「全く先が読めない環境」での経営判断が常に求められた一年であった。
この一年を振り返ると、我々は「経営の畑を耕し、種まき、根をはる一年~ 1年で終わらない経営の畑づくり、3年は企業づくりを~」と定時総会で決議したテーマに基づき、質の高い学びを追求してきた。5月の定時総会では、京都大学名誉教授の岡田知弘氏から、激動する外部環境の客観的な情勢分析をいただき、さらに11月経営フォーラムでは、都留文科大学の古屋和久教授を招き、「わからない」と言える「居場所」、すなわち社員が自ら育つ学習する組織文化の作り方を深く考えた。
また、組織の基盤強化にも注力した。事務局では迅速な月次決算と数値の透明化が実現し、運営改善と支出抑制の努力により、財務体質は改善した。また、AIを駆使して業務範囲が広がり、例会運営のサポート等、会員活動のサポート範囲を広げることができた。我われ栃木同友会は、多くの課題に向き合った2024年度の「畑を耕す」段階を終え、2025年度は活動の「種をまき、根がはりはじめた」年であると総括できる。
その上で、昨今の外部環境の変化を踏まえ、我々栃木同友会は、活動の柱を明確にしたい。それは、「何が何でも生き残るJ「仲間と共に生き残る」「暮らしと共に生き残る」「時代を超えて生き残る」ための経営を深く探求し、会員がそのための学びと体験を得られる場となることである。
この不透明な時代を乗り越えるには、外部環境の把握と、自社の揺るぎない理念と社員の信頼関係こそが不可欠である。
来たる2026年、我々の学びの場はさらなる高みを目指す。5月の総会では、「絶対にあきらめない~地域と共に存続を目指す銚子電鉄の挑戦~」と題し、竹本勝紀社長に登壇を依頼する。竹本社長からは、数字による現状把握、仮説と実行という徹底したPDCAサイクルに基づく、時代を超えて生き残るための実践的な経営姿勢を学ぶ。
激変の時代だからこそ、我われ中小企業家は同友会という場で、学びの場を深め合い、互いに育ちあうことが重要です。この学びと体験の場は、必ずや皆さまの企業づくりに役立つはずである。熱意をもって活動にご参加ください。
[文責]斎藤 秀樹
栃木県中小企業家同友会 代表理事/(株)ウィステリアコンパス
Posted on 2025年12月26日(金) 13:19
News Topic 01 栃木のNEWS
2025経営フォーラム
「わからない」からはじまる「ひと」の育ち合い
~学ひ合う文化をすべての組織に~
11 月21 日、栃木県総合文化センターにて栃木中小企業家同友会2025 経営フォーラムが開催された。同友会会員30名、オブザーバー11名の合計41名が参加され、基調講演では都留文科大学教育学部教授の古屋和久氏を講師としてお招きし、ご講演いただいた。
私が初めて古屋先生を知ったのは、「学び方を学ぶ」をテーマとした2023年県央支部10月の映像例会だった。『28の瞳~学び合う教室~ NHK ETV8』(2012年2月にNHKで放映)における、古屋先生の独特で斬新な子どもたちへの関わり方は印象深かった。当時、私と同様に古屋先生の教育方針に魅了された参加者と、実際にお会いしてもっとお話を伺いたいと感想を伝え合った記憶がある。
その後、2024年8月神奈川県同友会開催の講演会で古屋先生が講演されると聞き、私自身、数名の方と迷わずオブザーバーとしての参加を決めた。実際に講演を拝聴し、念願かなって直接お会いできた時の感動は忘れられない。おそらく今回の経営フォーラムの企画は、この時点でほぼ決まっていたように思う。
基調講演の18時35分から約80分間、参加者全員、古屋先生の独特な雰囲気での語り方に菓中して聞き入っており、とても短く惑じた。その後約50分間、グループに分かれての討議や活発な話し合いが行われ、数グループからの質問に古屋先生が応えられ、最後は座長の小岩代表理事のまとめで会を締めくくり閉会となった。
古屋先生が考える教育とは、児童や学生が自主的に問題点に向き合い、仲間たちと協力し合って答えを導き出す経験を活かし、教師はその一助となることが望ましいということかもしれない。言い換えると、教室で学ぶ者は、柔軟な考え方を持ち、相手の考えを尊重し、仲間と関わりながら成長していくことが大切なのだ。教師が解決策を与えてばかりでは、本当の意味での成長には繋がらないとも捉えられる。この事は中小企業家同友会の考え方と近似しているのではないか。
「わからない」ことを「わかった」振りをしてしまうよりも、「わからない」ということを素直に認め「わかろうとする」ことが非常に大切なのだと、先に述べた2年前の県央支部例会時の映像でも伝わってくる。これは、私たち中小企業家にも言えることである。経営者自身、社員や関係業者に「わからない」と言えているだろうか。素直に「わからない」を言い合える関係性を持つことは、自他ともに成長するためには必要なことだと考える。学校での「教室文化」は、会社内の「企業文化」にもおおいにつながるものな
のだ。
今回オブザーバーの中には6名の教職員が含まれている。6名の内訳は、中学校教諭2名、高校学校教諭4名であるが、講演後のグループ討議では、それぞれの立場で各々の考え方を伝え合い、私たちと共にグループ討議に参加され、教育関係者として今後のヒントを持ち帰られたなら幸いである。同友会のフォーラムや例会の企画の中で、産官学金の中の「学」に関わる方がここまで多く参加された企画は今までなかったのではないだろうか。
私たちにとっても、6名の教育関係者から間接的に私たちの中に落とし込めることが多くあったことも確かであり、今回の企画は、教育の観点から「学び合う文化の大切さ」をわかりあえる、非常に有意義なフォーラムであった。
今後、全県行事のテーマは、今回のテーマから引き継がれることとなる。学びの共同体はまさしく、栃木県中小企業家同友会の今後のあゆみを形容するものである。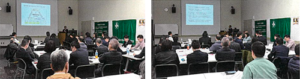
[文責]臼井 進
U-TEC株式会社 代表取締