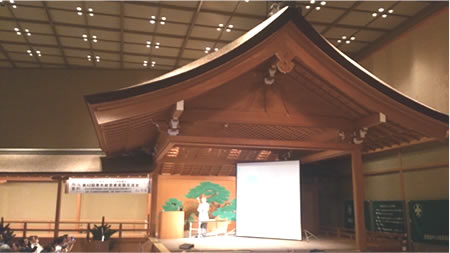Posted on 2015年2月6日(金) 14:38
News Topic 01 全国の話題 ~中小企業家同友会全国協議会から~
えっ!? 社員の給料も 課税されるって本当?
政府税制調査会が提言をしている「外形標準課税」が、われわれ中小企業にも拡大されるとどうなるのか?大雑把に言うと、赤字黒字に関係なく、企業に勤めている社員の給料にも課税され、雇用をしていけばいくほど経営の負担となる。外形標準課税により減税の恩恵を受ける企業も中にはあるが、その逆もある。自社は大丈夫でも販売先、仕入れ先等の関係先がおかしくなる場合もある。
法人税減税の代替財源としての外形標準課税拡大は、消費税増税に引き続き、確実に中小企業全体にとって増税となる。
8月21日に行われた中同協の第1回常任幹事会では、「中小企業家同友会は法人税減税に反対はしない。しかし、外形標準課税のような中小企業経営にそのしわ寄せを求められるものには反対していく」という方向性を確認した。
各地の同友会では、今回の外形標準課税適用拡大等の税制改正についての学習、地元選出国会議員に対し、中小企業の立場を理解し、この税制改正に反対していただこうとする運動を開始している。栃木でもこの動きに歩調を合わせいくつもりである。
[報告] 代表理事 八木 仁 (株)シンデン
Posted on 2015年2月6日(金) 14:35
News Topic 02 参加報告 第42回 中小企業家同友会全国協議会 青年経営者全国交流
和を以て貴しと為す in 奈良
~青年経営者よ 和の精神を以て
次の歴史の創造者たれ~
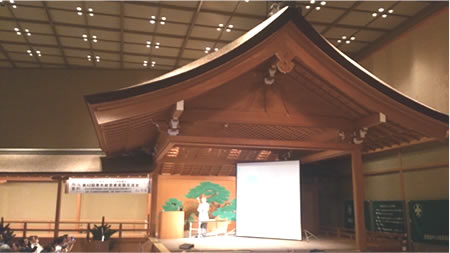
9月18~19日、奈良で開催された中同協の青年経営者全国交流会に参加した。1日目は14の分科会が開催され、私は第4分科会の「覚悟をもって経営やってますか?」都タクシー株筒井基好氏の報告に参加した。私のグループは経験豊富な経営者や後継者もいて、経営者の資質という部分にクローズアップした討論になり、人間力やリーダーシップなどが話題に上がった。グループ討論発表ではさまざまな考え方を得ることができ、また、参加者たちの「学び」に対する高い意識に大きな刺激を受け、熱意・知識をもらった。
2日目は株鵤工舎の宮大工棟梁の小川三夫氏の記念講演に参加した。法隆寺に魅せられ高校卒業後に単身で奈良へ。そこで修業を積み宮大工になった氏の話は一言一言に説得力があった。経験と技術に裏打ちされた職人ならではの話だった。
今後、このような経験を栃木県同友会の活動に活かしていきたい。
[報告] 県央支部長
中村悟志 / (株)アクティチャレンジ
Posted on 2015年2月6日(金) 14:35
活動報告 01 県央支部 【活動エリア】宇都宮市を拠点に活動中
8月 県例会
「人とのつながりが会社を変えた」

浜野慶一 氏
県央支部が主催した8月県例会(8/25開催 参加者25名)は、東京都墨田区で精密板金、金属プレスを行う浜野製作所の浜野慶一社長を報告者に迎えた。
父の死去に伴い社長になった氏は、工場が火災に遭う中で人の縁に支えられ、会社を存続させることができた。その後、あるきっかけから大学生のインターンシップ受け入れや産学官連携による製品の開発(電気自動車HOKUSAI、深海探査機江戸っ子1号など)を行い、現在も精力的に活動中だ。チャンスをビジネスに変える独自の視点や、あきらめずに継続することの大切さを学んだ。
次回の県例会(10/31)は中小企業問題の専門家、駒沢大学教授・吉田敬一氏の「これからの経済情勢と中小企業経営を考える」を予定。多数の参加を期待したい。
[報告]県副代表理事
石綱知進 / (株)共立
Posted on 2015年2月6日(金) 14:33
活動報告 02 県央支部、県北支部
県央支部例会(懇親会)
~秋の夜長にお酒となんでもディスカッション~

県央支部
9 月10日、「海蔵 県庁前店」にて第4回県央支部 例会(懇親会)が開催された。今年度の県央支部例会は、時事問題から経営をディスカッションしているが、今回は懇親会ということで12名の参加があり、お酒を酌み交わし、堅い話とフランクな話で盛り上がり、懇親を深めた。
[報告]県央支部副支部長
齋藤丈威 / 行政書士齋藤法務事務所
県北支部例会(企業訪問)

県北支部
8月25日、県北支部例会(企業訪問)を行った。総勢20名程で石井相談役の東陽機器工業株を訪問。活発に質問が飛び交い、有意義な例会となった。
その後、石井氏をはじめ6名で暑気払いを行い、和気あいあいとした和やかな雰囲気の中親交を深めた。
[報告]県北支部長
八木澤和良 / 八木澤社労士事務所
Posted on 2015年2月6日(金) 14:33
活動報告 03 共に育つ経営研究部会
ライブ感が魅力の学び場
~「共に育つ経営研究会」が始まって~
栃木同友会の会員の多くは何かしら事業承継に関わっていると思われる。「共に育つ経営研究会」は、そんな事業承継ならびに継承予定の会員を対象とし、時代に合わせて経営を変える企業事例を独自の視点で分析。ベテラン経営者も交え、参加者同士で討議する場である。
これまでに第4期まで開催。各期が3~4回で構成され、時折、臨時の研究会も開催した。シリーズを通して参加することで、理念を経営の中の数値の流れに反映させ、ゆくゆくは経営計画へ落とし込んでいくことを目指している。
同研究会の魅力は何といっても「ライブ感」にある。参加者はほとんどが経営者であり、その時々の話題について各々が意見を述べ、その意見を聞いて新たな気づきや発見を積み重ねていく。
研究会の開催は不定期だが、開催情報は栃木同友会のホームページで確認できる([栃木 中同友]で検索)。各自の都合に合わせて参加しても十分に楽しめる内容になっているので、多くの会員にぜひ参加してほしい。
[報告]共に育つ経営研究会
斎藤秀樹 /(株)ウィステリアコンパス